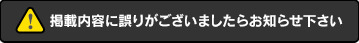昔の日本酒は、今のように透き通ったものではなく「にごり酒」ばかりだったそうです。
昔の日本酒は、今のように透き通ったものではなく「にごり酒」ばかりだったそうです。そんな時代、江戸の酒造り職人・鴻池善右衛門(こうのいけ ぜんえもん)という人物がいました。
ある日、彼のもとで働いていた男が失敗をしてしまい、善右衛門さんはその男をやめさせました。
ところが、恨みに思った男が「いやがらせ」で、蔵の中の酒樽に灰を投げ込んでしまったのです。
当然、酒は台無しになったと善右衛門さんは落ち込みました。
しかし翌朝、樽をのぞいてみると驚くことに、酒は透き通っていたのです。
灰が「にごり」を吸着し、偶然にも“清酒”が生まれた瞬間でした。
失敗やいやがらせと思える出来事の中にも、
新しい発見やチャンスが隠れている
まさに“転んでもただでは起きない”という教えのようです。
この季節、この話を読んでいたら、久しぶりに熱燗でも呑みたくなってきました(笑)