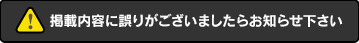昔の日本では、名字を持てるのは武士や貴族だけでした。
ところが明治時代になり、政府から「すべての国民が名字を名乗るように」というお達しが出ます。
しかし、いざ「名字をつけてください」と言われても、どう決めればいいのかわからない人も多く、
村の庄屋さんに相談して決めてもらうケースもたくさんあったそうです。
そのときに「お前は猫に似てるから、“猫田”でいいか!」
…そんな風に、見た目だけで名字が決まってしまった人もいたとか(笑)
真偽のほどはさておき、明治初期には、こうした“ひらめき”や“ノリ”で生まれた名字が存在していたのです。
ちなみに、現在の日本にある名字は約29万種類。
名字がたった数千しかない中国と比べても、ものすごいバリエーションです。
?本当のところはどうなの?
・明治時代に名字を全員が持つようになったのは本当。
・1870年:「平民苗字許可令」…名字をつけていいよ、というお達し。
・1875年:「平民苗字必称義務令」…全員必ず名字を名乗りなさい、という義務。
・でも名字をどう決めたかは、かなり自由だった。
・自分の出身地、地形、屋号、職業や官職、先祖の名前や氏族名、好きな文字などを元に名乗る人も多かった。
・読み書きができなかったり、迷った人は、庄屋さんなどに相談するケースもあった。
・そのときに「顔が猫っぽいから猫田でいいんじゃね?」みたいなノリも、ゼロではなかったかも…という、ちょっと笑える話。
このエピソード、実は現場仕事にも通じるヒントが詰まっています。
①とりあえず決めて、前に進む力
庄屋さんは悩まず決めました。
「完璧な正解」よりも「今、この場での最善」を選んだのです。
→ 仕事でも、「考えすぎて動けない」より、「まずやってみる」姿勢が大切です。
②臨機応変な判断と、気づきの力
「猫っぽいから猫田」とは、ある意味その人の特徴をよく見ていた証。
人の個性をよく観察し、的確に捉える力は、接客にもマネジメントにも役立ちます。
→ 現場ではマニュアルより、“その人に合った対応”が喜ばれる場面が多いものです。
「完璧じゃなくても、“今の最善”を決めて動く」
私たちの仕事も、“とりあえずやってみる”ことで見えてくるものがたくさんあります。
迷ったら一歩踏み出す勇気と、周囲をよく観る目を持つこと。
それが、“名指しで選ばれる人”になる秘訣かもしれませんね。