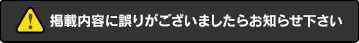実は昔の日本では「両」が使われていました。時代劇や落語でもおなじみですよね。その下には「分」や「文」という単位もあり、今とはまったく違う仕組みでした。
ところが明治4年(1871年)、政府が「新貨条例」を定め、新しい単位として「円」「銭」「厘」が導入されます。
なぜ「円」だったのかというと小判などのお金の形が丸いこと、そして国際的に見ても使いやすい名称だったからだそうです。
仕事にも通じる「円」の考え方
昔のお金は「両」「分」「文」とバラバラでしたが、「円」に統一されたことで、誰にでも分かりやすく、国際的にも通用する仕組みになりました。
これは私たちの仕事にも同じことが言えます。
それぞれがバラバラのやり方をしていたら、お客様は混乱してしまいます。ルールや基準をシンプルにし、全員で同じ形にそろえることが、安心していただけるサービスにつながります。
小さな“統一”の積み重ねが、大きな信頼へと変わっていくと改めて感じました。